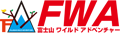撮影:2023.7.30
妖精の森では、ギボウシ(ウルイ)が見られます。

ギボウシは、地域によっていろいろな呼び方があり、「ウルイ」「ギボシュ」「ギボ」「ギボシ」「ゲーロッパ」「タキナ」などの名前で親しまれています。
日本の伝統的な山菜としても知られ、食用や薬用として利用されています。あくがほとんどないため、特に下処理は必要ありません。野菜のように食べられるので、オススメの山菜です。
生食も出来ますが、特徴であるヌメリは、生のまま食べても感じられませんので、ゆでたりたたいたりして調理すると良いでしょう。
みそ和えや浅漬けで食べるのが定番ですが、味噌汁やスープ、パスタの具材に加えるのもおすすめです。
夏には葉が固くなるので、サッと揚げて天ぷらにすると美味しく食べられます。

撮影をした7月30日は、ギボウシの花のつぼみも見られました。花も天ぷらにして食べられます。
ちなみに、「ギボウシ」の由来は、蕾の形が寺院や橋に飾られている「擬宝珠(ぎぼし)」に似ていることから付けられたそうです。
薬用としては、開花期に全草を陰干しするか、必要時に全草を採取して利尿に用います。また、生の茎葉や根をつき砕いた汁をそのまま服用すると、悪性の腫れ物に効き目があるとされています。
春先のギボウシは、歯ざわりが良く淡白な味で人気の山菜ですが、若芽が毒草の「バイケイソウ」に似ており、誤食による中毒などの事故も発生しているので注意が必要です。
見分け方は難しくないので、以下を参考に山菜ライフを楽しんでください。
バイケイソウに御用心!(茨城県)
なお、花言葉は、「落ち着き」「鎮静」「変わらない思い」「静かな人」です。
※富士山ワイルドアドベンチャー(FWA)では、許可のない山菜採取は禁止とさせて頂いております。

■名前
ハハコグサ
何科
キク科ハハコグサ属の越年草である
生育場所
道端や畑などに見られる小型の草
特徴
春の七草の1つ、御形でもあり、茎葉の若いものを食用にする
花の冠毛も起毛状にほおけ立つことから、別名ホオコグサとよばれる
花言葉は、「いつも想う」
春になると茎を伸ばして草丈15 – 40センチメートル (cm) になる
花期の春から初夏にかけて(4 – 6月ころ)[6]、茎の先端に頭状花序の黄色い花が密に集まって多数咲かせる

■名前
ヤブガラシ
何科
ブドウ科ヤブガラシ属の一種である。つる植物
生育場所
道端、林縁、荒れ地などに生え、市街地では公園のフェンスなどによく絡まっている
特徴
別名ビンボウカズラ(貧乏葛)つるの長さは 2 ないし 3 メートル
葉と対生する巻きひげが伸びて他のものに巻き付き、覆い被さって葉を茂らせる
花は直径約 5 ミリメートルで薄緑色の花弁4枚と雄蕊が4本雌蕊が1本ある
6 – 8月ごろ徐々に開花する

■名前
ツユクサ
何科
ツユクサ科ツユクサ属の一年生植物。
生育場所
自生地は日本全土を含む東アジア
特徴
朝咲いた花が昼しぼむことが朝露を連想させることから「露草」と名付けられたという
花の鮮やかな青色から青花(あおばな)などの別名がある。
高さは15~50cmで直立することはなく、茎は地面を這う
雌しべが1本、雄しべが6本で成り立っている。
アサガオなどと同様、早朝に咲いた花は午後にはしぼんでしまう。

■名前
イワギボウシ
何科
岩擬宝珠:ユリ科
生育場所
岩場深山谷沿いの岩上に生える多年草で高さ10~30cmになります。
特徴
開花は8~9月と遅い
花は40cmくらいの長い花茎を斜めに、ときには下に伸ばして、先端に白淡紫色の漏斗状の花を下向きから横向きに10数個つける。
花言葉は落ち着き、沈静、変わらない思い、静かな人などである

■名前
へびいちご
何科
バラ科キジムシロ属に分類される多年草の1種
生育場所
ヘビがいそうな所に生育する
特徴
毒があるという俗説があり、ドクイチゴとも呼ばれるが、無毒。
ジャムに加工可能
全草や果実を乾燥させたものは生薬として利用